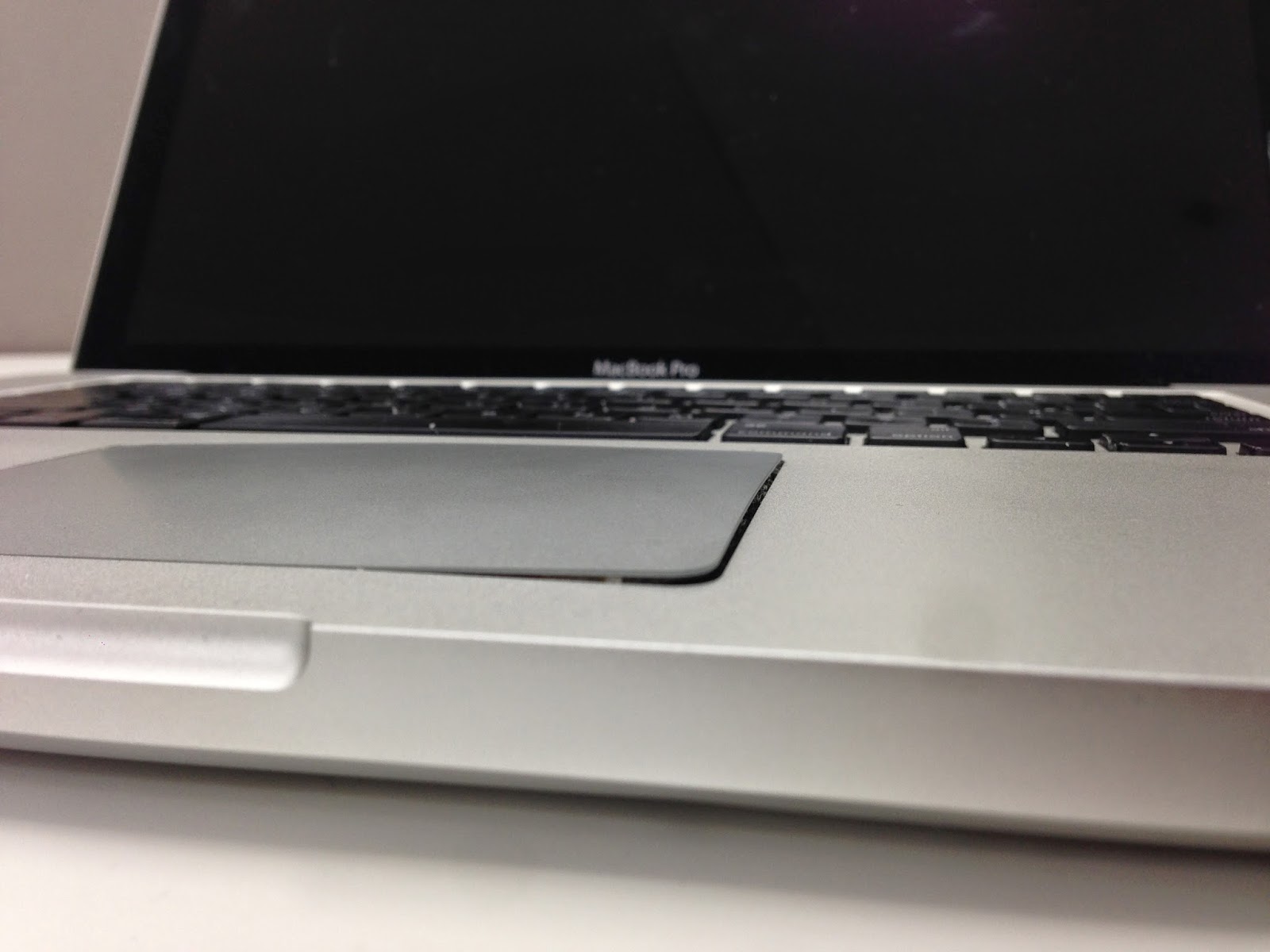7月はほぼ日本にいた。
今の会社の仕事において7月、8月の過ごし方はとても大事である。3月の年度末にむけてじわじわと忙しくなるパターンの中、夏は大きなイベントが少ない。
だから毎年3月の年度末になると思う。なぜ(比較的余裕のある)7・8月にもっと前倒しで仕事をやっつけておかなかったのかと。スラムダンクの三井寿の悔恨がほんとうによくわかるのである。
しかし今年は新たな役職について、大学院の研究もしている。比較的余裕のあるはずの7月も決して時間があるわけじゃない。そんななかで趣味の本を読んだり、実家に帰ってリフレッシュしたりと充実してすごせた。
でもやはり南の島で3日くらいボケーッとすごしたいなぁ。
 |
| Boston Museum |
 |
| いただいた北海道メロンをつかったアイスクリーム。うまい |
 |
| 珍しい弁当のケースを各種取り揃えて売っている店 |
 |
| 旧図書館は入り口が3階にあり、そこから各書庫におりていくというダンジョンのような作り |
 |
| 祖母の手作りおから |
 |
| 「くれてなお 命の限り 蝉しぐれ」ヤス、いいこというなぁ。 |
 |
| 地元の映画館で現在上映中の劇団ひとり監督「青天の霹靂」のロケが行われ、その場所がそのままになっている |
 |
| 僕が Mt. fictionousと呼ぶ田舎の山 |
 |
| はじめて奈良の大学へ。 |
 |
| 珍しいね。高校の同級会 |
今月のぐっときた言葉:
ラーメン屋においてあったAERAに小島慶子というラジオのパーソナリティがいいことを書いていた。
いかに問い、いかに答えるかの道すがら、自分に見えた風景は人とは違う。たとえ辿り着いた答えが同じであっても、自分の学びは固有のものであると思える人は豊かだ。けれど、自分の学びだけが優れていると思う人は孤独だ。あらゆる学びは、他者と繋がるためにあるのではないか?生活するために、誇りを持つために、孤独に耐えるために、それが自分一人の苦しみではないと知るために。
"教育サイコー!②の5 小島慶子の幸複論", AERA,2014/5
学びは他者と繋がるためにあるというのは至言である。